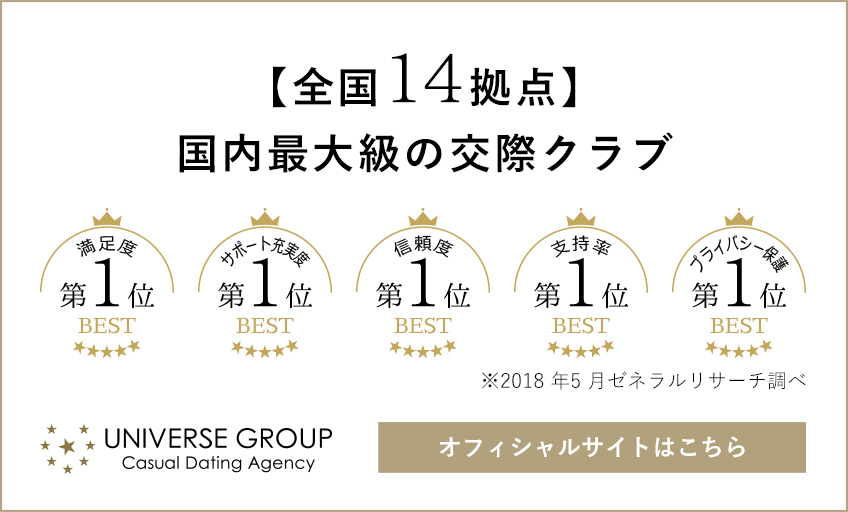私は昔、パパ活を始めようとして、結局やめた経験があります。
パパ活は、可愛い女の子だけが稼げる物だと思っていたので、私には自信がなかったのです。
可愛いとか可愛くないとか、そんなルッキズムに縛られているのは自分自身だとは気づかずに、自分自身の容姿をおとしめては、自分で自分のことを嫌いになっていました。
そんな私が東京という街で、パパ活を始めようと思った理由について書いていきたいと思います。
パパ活を始めた理由は、シンプルにお金がなかったからです。
私は、ライターや作家を目指して田舎から上京してきた、よくある「夢を目指す若者」という感じでした。
大学時代は関西にいた私ですが、大学では休学と留年を繰り返し、合計7年ほど在籍していました。
その時点で私は人生につまずきを覚えていて、普通の人生を送ることを夢見ることは無理なことだと信じきっていました。
なぜ大学を休学したかというと、大学が肌に合わなかったからです。
勉強するのは好きでしたが、その頃に知り合った友人たちと気が合わず、トラブルとなってうつ病になり、結局休学することになりました。
ストレートで入学した私は、卒業も同じくストレートでするものだと思っていたので、休学した時はまるで人生が終わったかのように感じました。
今思えば、休学するなんて別に変わったことではないし、休学した時間を別のことに割けるのなら、それも人生経験なんじゃない?なんて思うのですが、その時の私はもうパニック。
引きこもりになり、大学時代に発症した醜形恐怖症と闘うことになりました。
ちなみに醜形恐怖症とは、自分の顔や体のささいな欠点に対して必要以上に恐怖を覚えたり、苦痛を覚えたりすることです。
Twitterでもたくさんの女の子が悩んでいて、私たちにとってこの体や顔面は、一生闘っていくものなのだな、と思わされます。
pjさんたちも、醜形恐怖症に悩んでいるひとは多いのではないでしょうか?
自分のことを認めてあげられない、それだけがこんなに苦しくて、私たちは毎日鏡を見るたびに絶望する。
そんな日々の中で見出せる希望を必死で掴み取りながら、今も生きている。
私は、今もそんな気持ちです。
私が引きこもりから立ち直るのには、およそ2年の月日がかかりました。
あの頃は外に出ることもできず、自分が街を歩けばみんなに笑われる、そんな風に思っていました。
立ち直った後は無事に大学に通ったものの、薬と通院は続き、卒業論文が書けずに留年しました。
卒業論文を書くことは本当に嫌で、最終的に鬼滅の刃で書くという、善逸もやめとけば?というレベルの卒業論文を出したことは完全に黒歴史です。
それでもなんとか卒業した私。
ただ、人生計画は狂ったままで、普通の就職もできないまま。
そんな私が唯一好きだったことが「書くこと」でした。
日記をつけるのが趣味だったので、その延長で長い文章を書こうと思い立ったのです。
そしてずっと憧れていた東京に上京することにしました。
その頃、バイトが決まっていたので安心して上京したのですが、やってきたのは「コロナウイルス」。
突然の外出自粛に、緊急事態宣言。
人生で見たことがない文字が踊る世界の中で、言い渡されたのは解雇でした。
東京とも呼べないような片隅、西日が差す部屋で、私は絶望していました。
家賃の見通しも立たない中で、すぐに稼げるバイトとして思いついたのがパパ活でした。
パパ活について調べては、毎日悩む日々。
「大人」や「?」という単語があることも、その頃に知りました。
そして、登録したパパ活アプリは「ペイターズ」。
自分の大学生の頃の一番笑顔の写真を登録しました。
今思えば、ある種の反抗だったのかもしれません。
大学という場所で、学んできたことがこんな形で活かされることになるなんて、とやさぐれた気持ちでいました。
そしてやってきたメッセージは
「大人、1.5、定期でお願いします」。
私でもわかった、相場よりずっと低いことなんて。
東京という街で、自分に値段がつけられたような気がして、まるで野菜売り場に並べられたようで。
ただ、それでも価値をつけてくれるひとがいることがありがたくてしょうがなかった。
私にとってそれは希望の光でした。
けれど、私がそんな価格で受け入れてしまったら、みんなその価格でよくなってしまう。
そう思い、私は結局アプリを閉じました。
きっとこういうことに手慣れている人なら、ご飯だけでもお金がもらえるのだろうけど、初心者の私は全く分かりませんでした。
これがパパ活を始めた理由です。
そのあと、私は結局日雇いのバイトを繰り返すことで、無事に家賃をゲットすることができました。
その時期にちょうどコロナワクチンの接種会場のバイトが大量にあったことも大きく関係しました。
私にとって、この街は戦場です。
夢と希望が溢れている世界で、その屍が転がる街。
毒々しいネオンに照らされた夜の街で、シーソーゲームを繰り返し、コンクリートジャングルの中で、冷え切った人間関係と人情が交差する。
そんな戦場の中で、掴み取りたい未来のために、日々防護服を着て銃をぶっ放す。
隣に住んでいる人が誰かも知らない、私のことを誰も知らない街で生きていく。
そう思うと、少しだけ上を向けるような気がするのです。
誰も守ってくれない戦場で、私が私のことを愛する。
それだけを目指して、私も今日も闘っています。